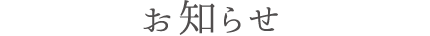第18回 奉納四條流庖丁儀式
更新日 2025年07月10日
庖丁儀式は日本王朝時代の厳粛な儀式であり、古典文化生活の一表情です。
「源氏物語」「宇治拾遺物語」の中にも記されており、古い時代からおこなわれていました。
そのはじめは殿上人(公卿)や、大名が賓客を我が家に招いた場合に、その家の主人が心から歓待する意味で、まず、主人みずから包丁をとって包丁ぶりを見せてご馳走したのであります。
従って、「庖丁式」は、厳粛な儀式であるとともに、平和な大宮人の風流優雅な氣分を生活の一端を表現した社交儀礼とも言えます。
第18回 奉納四條流庖丁儀式
日 時:令和7年7月16日(水) 午後1時30分
場 所:椿大神社 外拝殿
式次第:第一部 式題「光来之鯉」
奉仕包丁人 世古 柏世
介添人 速水 政利
介添人 森 一真
納め之義 古川 柏滉
第二部 式題「蓬莱之鯛」
奉仕包丁人 武藤 柏藤
鯉飾之儀 速水 政利
包丁飾之儀 世古 柏世
三重社中一同
解説 四條流門人準師範三重社中 羽田 柏涼